4.新しい時代の2型糖尿病治療 ─食欲は制御できるのか?
─予防・治療・啓発の将来像─
4.新しい時代の2型糖尿病治療 ─食欲は制御できるのか?
Vol.39 No.6(2022年11・12月号)pp.630-635

中里雅光 Nakazato, Masamitsu
宮崎大学医学部医学科 生体制御医学研究講座,大阪大学蛋白質研究所
はじめに
肥満症では,体重の3%以上が減少すれば糖代謝・脂質代謝・脂肪肝などが改善する.しかし,長期間の体重減少に成功する肥満症患者の割合は低く,入院などの強力な介入により減少した体重も,介入が終了するとリバウンドすることが多い.体重はエネルギー収支のバランスで増減するが,最も大きく影響するのは摂食である.摂食は恒常的(homeostatic)調節機構により制御されているが,ヒトの場合は「おいしい」食物を目の前にした場合の過食など,恒常的調節とは無関係な摂食行動もみられ,これは快楽的(hedonic)摂食と呼ばれる.恒常的調節では視床下部や脳幹が中心となり,末梢臓器(消化管・肝臓・膵臓・脂肪組織・筋肉など)からのエネルギー代謝・蓄積状態,栄養素,消化管ペプチド,レプチンなどのシグナルが調節している.一方,快楽的調節では視覚,嗅覚,味覚,食後の快感や満足感,記憶などを含めた大脳辺縁系や大脳新皮質などの上位中枢からの制御も受けており,肥満者でみられる薬物依存症に類似した摂食行動(food addiction ともいわれる)に関与している.脳内や末梢臓器には,食欲亢進または食欲抑制作用をもつ多数の摂食調節ペプチドが産生され,各部位をつなぐ神経回路網や血流を介して複雑に情報伝達され,相互作用している.減量を成功させるためには,ヒトの摂食調節機構の詳細を解明し,そのメカニズムを応用した治療法を開発することが重要となる.近年,この分野の基礎研究は大きく進歩しており,長期間の減量効果を示す薬剤も開発されている 1).本稿ではすでに海外で承認され,わが国でも近い将来に処方が期待される食欲制御薬を中心に,摂食機序との関係や効果を紹介する.
 糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
毎号、明日の臨床に役立つ時宜を捉えたテーマを取り上げ、各分野のエキスパートが徹底解説。
専門医の先生はもちろんのこと、これから専門医を目指される先生まで、ぜひアップデートにお役立てください。
医薬品・医療機器・検査機器
-
経口薬
-
注射薬
-
医療機器・検査機器
最新特集記事
-

インクレチン関連薬による糖尿病網膜症-最新エビデンスとその治療戦略-
【学会レポート】第40回日本糖尿病合併症学会 -

低血糖の回避と血糖変動の是正が心血管疾患の重要な治療戦略に
【学会レポート】第40回日本糖尿病合併症学会 -

肥満関連腎臓病の病態と減量・代謝改善による治療の効果
【学会レポート】第40回日本糖尿病合併症学会 -

リアルワールドデータから見るこれからの糖尿病治療戦略
論考百選 -エキスパートたちの視点- -
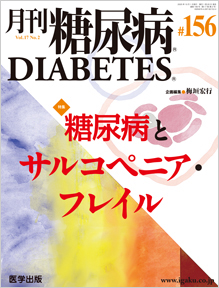
月刊糖尿病156号(Vol.17 No.2 2025)特集「糖尿病とサルコペニア・フレイル」
Book Select ー糖尿病関連書籍紹介ー -

第21回「“もったいない”が仇に」
4コマ劇場「糖尿病看護の“あるある”体験談」 -

Vol.21 「両方ともしっかり治療」 が大事です 糖尿病に合併する 「高血圧」
よりよい糖尿病看護を目指して -

透析患者だった私がたどり着いたSDMのかたち
【学会レポート】第70回日本透析医学会学術集会・総会
よく読まれている記事
関連情報・資料
-
論考百選 -エキスパートたちの視点-
糖尿病医療の現場で活躍する専門家が、最新のトピック、医薬品・医療機器に関する情報、医療課題などをテーマに独自の視点で掘り下げて解説。 -
学会レポート
様々な学会を取材し、医療従事者の方々に今、特に知ってほしい演題を編集部が厳選。糖尿病に関係する話題はもちろん、医療トレンドとしても注目のテーマを簡潔レポート! -
慢性腎臓病とSDM~life goalsと療法選択~
年々増加傾向にある慢性腎臓病。糖尿病性腎症や慢性腎臓病の進展防止とともに、腎代替療法、さらにはSDMに焦点をあて、各分野のエキスパートが情報を提供。 -
糖尿病治療に役立つ情報をお届けするDexcom Express
Dexcomの新しいリアルタイムCGM G7の情報をはじめ、糖尿病治療に役立つ情報をアニメーションや動画で分かりやすく提供。【提供】デクスコムジャパン -
肥満症認知向上プログラム【セミナーレポート】
肥満症の基本から患者さんへのアプローチ、新ガイドラインを踏まえた診療、減量・代謝改善手術などの新たな治療選択肢などを紹介。【提供】ノボ ノルディスク ファーマ -
医療スタッフのギモンにこたえる グリコアルブミンQ&A
血糖管理指標である”グリコアルブミン”の基本から使い方まで、医療スタッフの皆さんの疑問にこたえるグリコアルブミンに関するQ&Aコーナー。【提供】ナガセダイアグノスティックス -
糖尿病ネットワーク
1996年より糖尿病に関する情報を発信する糖尿病患者さんと医療スタッフのための情報サイト。ニュースやイベント情報に加え、患者さんが交流できる掲示板が人気。 -
国際糖尿病支援基金
海外の団体と連携し、途上国の患者さんの支援活動を行っている基金。同じ病気を持つ仲間として何ができるかを考える。豊富な海外の糖尿病事情を紹介。







