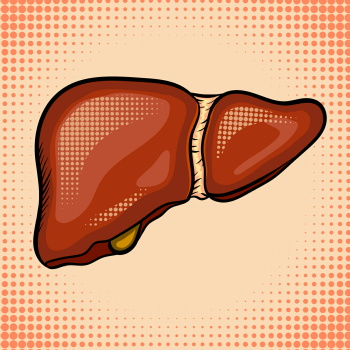生活習慣介入もメトホルミンも心血管疾患や脳卒中の予防には効果なし 2型糖尿病の発症予防には効果的

生活療法やメトホルミンが2型糖尿病予防に有効であることは、すでに明らかになっている。ただし、糖尿病に関連する心血管疾患発症に対するそれらの介入の有効性はまだ明らかでなく、Goldberg氏らはその点を、DPP(Diabetes Prevention Program)とDPPOS(DPP Outcomes Study)により検討した。
DPPは耐糖能障害のある3,234人に対し、メトホルミン(850mgを1日2回)、または厳格な生活療法により3年間介入し、プラセボ群との2型糖尿病発症リスクの差を検証。双方の介入群で2型糖尿病発症リスクの低下が認められ、特に生活療法群でより大きなリスク抑制効果が示されていた。DPP終了後のDPPOSでは平均18年間、参加者全員にマイルドな生活療法による介入が継続され、DPPのメトホルミン群にはHbA1cが7%以上の場合、同薬の処方が継続された。
主要評価項目であるMACE(非致死性心筋梗塞・脳卒中、心血管死)発生率は、メトホルミン群、生活療法群ともに、以下に記すようにプラセボ群との間に有意差がなかった。メトホルミン群対プラセボ群はハザード比(HR)1.03(95%信頼区間0.78~1.37、P=0.81)、生活療法群対プラセボ群はHR1.14(同0.87~1.50、P=0.34)。
年齢、性別、人種/民族、糖尿病発症の有無で層別化したサブグループ解析の結果、いずれについても有意な交互作用は認められず、結果は一貫していた。また、副次的に検討された、心不全または不安定狭心症の発症や入院、冠動脈または末梢動脈への血行再建術の施行、冠動脈造影により診断された冠動脈性心疾患、心電図所見により判定した無症候性心筋梗塞についても、有意なリスク差は見られなかった。
著者らは結論として、「メトホルミンも生活療法も、2型糖尿病の発症抑制には有効であるにもかかわらず、21年間にわたる追跡中のMACEリスクを抑制しなかった」とまとめている。考えられる理由として、「スタチンや降圧薬による血糖以外のリスク因子の管理状況が向上したこと、プラセボ群も含めた参加者全員にマイルドな生活療法介入が行われたこと、メトホルミン群ではその処方率が低下したことなどが、結果に影響を与えた可能性がある」としている。
なお、DPP/DPPOSには複数の製薬企業・栄養関連企業が、医薬品・医療機器・医療資材を提供した。また、一部の著者が製薬企業との金銭的関係の存在を明らかにしている。
[HealthDay News 2021年5月27日]
Copyright ©2022 HealthDay. All rights reserved.
Photo Credit: Adobe Stock