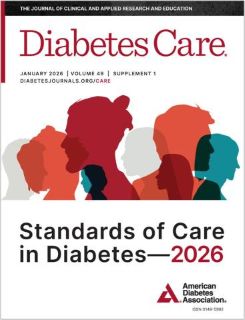【新型コロナ】重症患者への人工呼吸器・ECMOの導入 患者や家族にどう説明しているかを調査 デジタルの活用、患者の事前意思(ACP)が重要
COVID-19治療に対する人工呼吸器の導入基準やECMO開始基準を設けている施設は3分の1程度で、治療開始時点で重症化リスクおよび人工呼吸器やECMOの使用可能性について説明しているケースが多いことが分かった。

患者家族が濃厚接触者である場合も多く、電話による口頭での説明が多い
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療で、肺炎が重症化した患者には人工呼吸器が使用され、さらに呼吸状態が悪化した患者には体外式膜型人工肺装置(ECMO)を使用する場合がある。これらの治療の際に、患者は薬剤によって一時的に意識のない状態になるため、意思疎通がとれなくなる。また、患者は、感染予防対策のために隔離した環境下での治療や療養が必要となる。患者の代理人となる家族でも、患者と同居している場合には濃厚接触者となることで隔離が必要となることがある。
このようにコミュニケーションのとりにくい環境にありながらも、患者およびその家族が治療について理解したうえでその治療を受けるためには、医療者が治療に対してどのように説明をしているかが重要なポイントのひとつとなる。そこで、研究グループは、同感染症治療に従事する医師が、患者およびその家族にどのように説明し同意を取得しているかを把握するために、インターネットを用いたアンケート調査を実施した。
調査は、東京医科歯科大学生命倫理研究センターの吉田雅幸教授、慶應義塾大学医学部麻酔学教室の森崎浩教授らの共同研究グループによるもの。
対象となったのは、「ECMOネットワーク37施設」(国内でECMOを所有している医療機関から成る有志ネットワーク)に所属する医師37人(各施設1人)とし、うち15人(15施設)から回答を得た(回答率40.5%)。調査期間は2020年12月1日~2021年1月17日。
「COVID-19患者に対する人工呼吸器およびECMO装着に関するガイドラインの作成」について、ガイドラインを作成していたのは、回答施設の33.3%だった。ガイドラインの項目として、人工呼吸器およびECMOの「適応基準」を含めていたのは回答施設の100.0%。一方、人工呼吸器およびECMOの「離脱基準」を含めていたのは回答施設の75.0%、「中止基準」を含めていたのは回答施設の50.0%だった。
また、「COVID-19重症患者に対する説明もしくは同意取得の方法」について、治療に関する説明の多くは、医師と患者以外の複数名がいる状況で行われていた。文書は用いず、口頭による説明や同意取得が主に行われていた。 「説明時の状況で、説明をする医師と説明を受ける患者の他に同席者がいた」と回答したのは83.3%。その同席者の内訳としては、看護師75.0%、家族58.3%、他の医師41.7%だった。回答者の83.3%が、「患者への説明および患者からの同意は口頭で実施した」という回答だった。
「呼吸状態が悪化した場合に気管内挿管をして人工呼吸器による治療をする可能性」について、患者に対しては回答者の91.7%が、家族に対しては回答者の90.9%が説明をしていた。また、「人工呼吸器での呼吸サポートが限界に達した場合に、より体に負担のかかるECMOを使用する可能性」について、患者に対しては回答者の83.3%、家族に対しては回答者の100.0%が説明をしていた。
さらに、COVID-19で入院する患者の家族は濃厚接触者である場合も多く来院不可能なため、電話などによる口頭で病状説明を行うことが多いことも分かった。そのため、具体的な患者の状態を伝えることが困難である実態も明らかになった。
デジタルデバイスの活用、ガイドラインの作成が求められる 患者の事前意思(ACP)も重要
COVID-19の治療現場では、感染症対策の一環から、対面による文書同意ではなく、遠隔かつ口頭で治療に対する説明と同意取得が行われている現状が明らかとなった。より良い説明を実施するために、遠隔であっても説明者と患者およびその家族が互いの顔や様子を見られることや、説明時に文書や図を示すことができる環境が必要であることが考えられる。
これらを可能にできる方法としては、「デジタルデバイス(パソコンやスマートフォン、タブレットなど)」を用いた説明や同意取得方法の確立と、それらを使用できる環境整備だ。同時に、患者や家族でもデジタルデバイスを使用できる環境が求められるため、国民全体におけるデジタルデバイスの普及も新たな課題として挙げられた。
人工呼吸器およびECMOの装着に関するガイドラインの作成率は回答施設の3分の1程度だったが、同感染症は症状が急激に悪化する可能性があり、患者の容体や鎮静を必要とする治療(人工呼吸器やECMOの装着など)によって患者自身が意思表示のできない状態になる場合もある。治療方針に関する同意説明の際に、患者の意志決定に重要な情報が漏れなく提供されるためには、ガイドラインの作成とそれをもとにした医療者の同意説明の実施が求められる。
「治療や療養に関する患者の事前意思(ACP:Advance Care Planning;)が重要となることから、同意説明の際には医師と患者がACPについて話し合い、確認をすることが望ましいことが考えられる」と、研究グループは述べている。
東京医科歯科大学 生命倫理研究センター
慶應義塾大学医学部 麻酔学教室