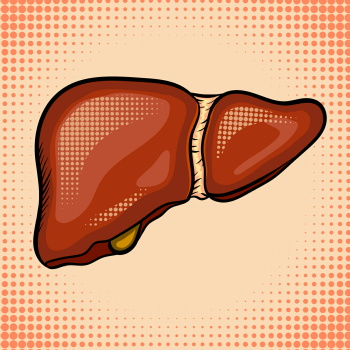非肥満メタボと関連する因子は男性・高齢・体重増加・喫煙・歩行速度・摂食速度・飲酒

国内で現在行われている特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満を基盤として発症するとされる複数の心血管リスク因子が重複した状態である、メタボリックシンドローム(MetS)をターゲットとして行われている。MetSの診断は内臓脂肪型肥満に該当することが必須であるため、複数の心血管リスク因子が重複しハイリスク状態と考えられる人であっても、肥満でない場合は積極的な保健指導の対象とはならない。今回発表された研究結果は、このような非肥満MetS者の生活習慣関連因子を明らかにしたもの。
研究対象は、製造業5社の健保組合が実施した2015年の特定健診受診者のうち、解析に必要なデータに欠落のない4万7,172人。統計解析の結果、非肥満者(2万8,720人)、肥満者(1万8,452人)ともに、男性、高齢、20歳時から10kg以上の体重増加、喫煙習慣、歩行速度の遅さ、摂食速度の速さ、大量飲酒という因子と、MetS構成因子を複数有することの有意な関連が明らかになった。
これらの因子のうち、歩行速度と摂食速度を除いて、肥満者よりも非肥満者の方が、MetS構成因子を複数有するオッズ比(OR)が高い傾向にあった。具体的には以下の通り。
男性であることは、非肥満者ではOR2.67、肥満者ではOR1.91。年齢が50代であることは、同順にOR3.09、1.88、60~64歳ではOR5.93、2.81。20歳時から10kg以上の体重増加では非肥満者がOR1.67、肥満者はOR1.45、喫煙習慣ありではOR1.24、1.16、1日の飲酒量2~3合未満ではOR1.81、1.44、3合以上ではOR2.50、1.52。
その一方で、定期的な運動習慣がないことは、非肥満者ではMetS構成因子を複数有することと有意な関連がなく、肥満者でのみ有意な関連(OR1.11)が認められた。
著者らは、「MetS構成因子を複数有する場合の生活習慣関連因子の大半が、肥満者と非肥満者の双方に共通して認められた。また、それぞれのリスク因子のオッズ比は、非肥満者の方が高い傾向がある」と結論。その上で、「MetS構成因子を複数有する人に対しては、肥満の有無にかかわらず保健指導を行う必要性が示唆される」と述べている。
[HealthDay News 2021年12月6日]
Copyright ©2022 HealthDay. All rights reserved.
Photo Credit: Adobe Stock