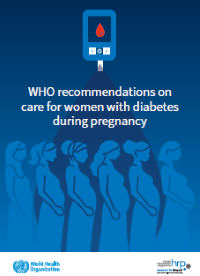京都大学などが「薬剤師教育プログラム」の開発へ 糖尿病患者の病態改善に薬剤師が積極的に関与
2019.03.28
京都大学大学院医学研究科健康情報学研究室は、2型糖尿病などの生活習慣病患者の病態改善を支援する薬局薬剤師の教育プログラムを、薬局を経営する2社と共同で開発すると発表した。

糖尿病患者に対する薬剤師の介入で血糖値や血圧が改善
教育プログラムの開発は4月から3年間の共同研究して行われ、京都大学大学院健康情報学の中山健夫教授と、京都大学大学院医学研究科および京都医療センター臨床研究センターの岡田浩氏らがリーダーに着任する。 これまで岡田氏らが取り組んだ「COMPASS」研究では、糖尿病患者に対する調剤薬局薬剤師により介入により、血糖値が改善することを実証。COMPASS研究は、薬剤師によるランダム化比較試験として2011年に全国の90薬局で実施された。薬剤師が糖尿病患者に積極的に関わる介入群と、HbA1c値を確認するだけの対照群で、登録患者の血糖値変化などを調査した。 この研究では、参加薬剤師は「動機づけ面接」や「情報提供用資料の使い方」を事前に学び、糖尿病患者に対し情報提供や言葉かけを実施した。その結果、対照群と比較して薬剤師が積極的に関わることで、HbA1c0.4%改善の成功率が約2倍になるという結果が得られた。薬局店頭での薬剤師の患者に対する数分程度の効果的な声かけや資料提供により、患者の自己管理やモチベーションを高められることが示された。 2014年には「COMPASS-BP」を実施し、薬局薬剤師の生活習慣改善支援により、高血圧患者の血圧改善効果を得られることを示した。2015年には「COMPASS-SMBG」を実施し、薬局薬剤師による自己血糖測定器を用いた生活習慣改善支援にも一定の効果があることを実証した。 今回の教育プログラムは次のステップとして、COMPASS研究で確立したエビデンスを全国の薬局薬剤師に広く実践してもらうことを目指す。中川調剤薬局の2社の賛同を得て共同研究で行われ、ウェブサイトなどを活用したe-ラーニングにワークショップ組み合わせた形態を想定。医療の質を評価する指標「クオリティインディケーター」の概念にもとづき、薬剤師が糖尿病患者や高血圧患者にどのように関わるべきか、数十項目にわたってポイントをまとめる。 プログラムの内容は「生活習慣改善・情報提供」「治療と状態についての教育」「検査値の評価」「受診勧奨」「アドヒアランス改善」「処方変更」など。薬剤師による糖尿病や高血圧の患者へのコンサルテーション業務の重要性が近年増大しており、それを支援するプログラムとすることを目指す。教育プログラムを受講した薬剤師が、現場で実践する上でのチェックリストとしても活用できるものにする。 「糖尿病や高血圧の患者数は急速に増加し、あわせて薬剤師に求められる役割も大きくなっている。服薬指導の考え方や、実践的なノウハウなど、医療の知識がありエビデンスベースでコミュニケーションができる薬局薬剤師だからこそできることが多い」と、岡田氏は述べている。 京都大学大学院医学研究科健康情報学研究室COMPASSプロジェクト(京都医療センター臨床研究センター)
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]