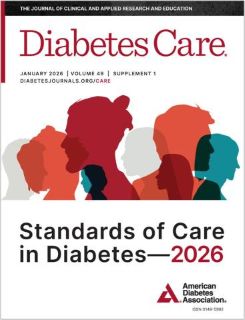糖尿病と歯周病 Up to date『月刊糖尿病』
月刊 糖尿病 2017年10月発行号 -主な内容-
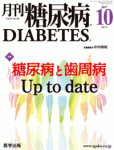
糖尿病と歯周病 Up to date
- 歯周病という疾患を知る
- 糖尿病になると歯周病になりやすいのか―疫学的研究成果から―
- 歯周病があると糖尿病になりやすいのか―疫学的研究成果から―
- 糖尿病と歯周病の関連性を科学する
- 血糖コントロールによって歯周病は改善するのか
- 歯周病治療は血糖コントロールの改善に有効なのか
- 糖尿病を有する患者に対する歯周病治療の実際
- 医科歯科連携の重要性と実際
- 超高齢社会に向けた糖尿病と口腔機能の連関
〔特集にあたって〕
口腔は、腸管、皮膚とともに、多くの細菌と共存している組織であり、その細菌叢の量的、質的なバランスが崩れることで、う蝕や歯周病といった疾病が発症する。本特集のテーマとなる歯周病の発症は、口腔内細菌の集合体であるデンタルプラーク(デンタルバイオフィルム)の量的増加、質的変化が生じ、Porphyromonas gingivalisなどのグラム陰性菌を主体とした細菌が増えることで、歯周組織に炎症が生じ、歯と歯周組織の付着を失うなどの組織破壊が生じると考えられる。一方、局所の感染だけで歯周病が成立するわけではなく、免疫応答、メタボリックシンドロームと呼ばれる糖尿病や肥満、高血圧などの全身的な因子もリスク因子として注目されている。さらに、喫煙やストレス(環境因子)、咬合力の問題(咬合因子)も重要視され、多因子疾患という捉え方もなされている。
歯周病は糖尿病の第6の合併症と言われるほど、その関連性が注目されてきている。糖尿病患者は歯周病に罹患しやすく、重症化しやすいことが明らかにされる一方、歯周病原細菌が引き起こす炎症は全身にとって軽微な炎症として影響を与えると考えられ、歯周病が糖尿病へ影響を及ぼすと考えられるようになっている。
本特集では、糖尿病と歯周病 Up to dateと題して、歯周病とはどのような疾患なのか、糖尿病患者は歯周病を発症しやすいのか、そのメカニズムはどう考えられているのか、血糖コントロールの良否が歯周病の進行に重要なのか、歯周病治療により糖尿病が改善するのか、などの情報共有が必要な項目について、現時点で明らかになっていることをまとめていきたい。本特集が、今後の積極的な医科歯科連携を行うための基礎的な知識となっていくことを期待している。
●A4変型・約130ページ 本体\2,700+税 2009年より発行 医学出版(03-3813-8722)
ホームページ→トップ/月刊糖尿病