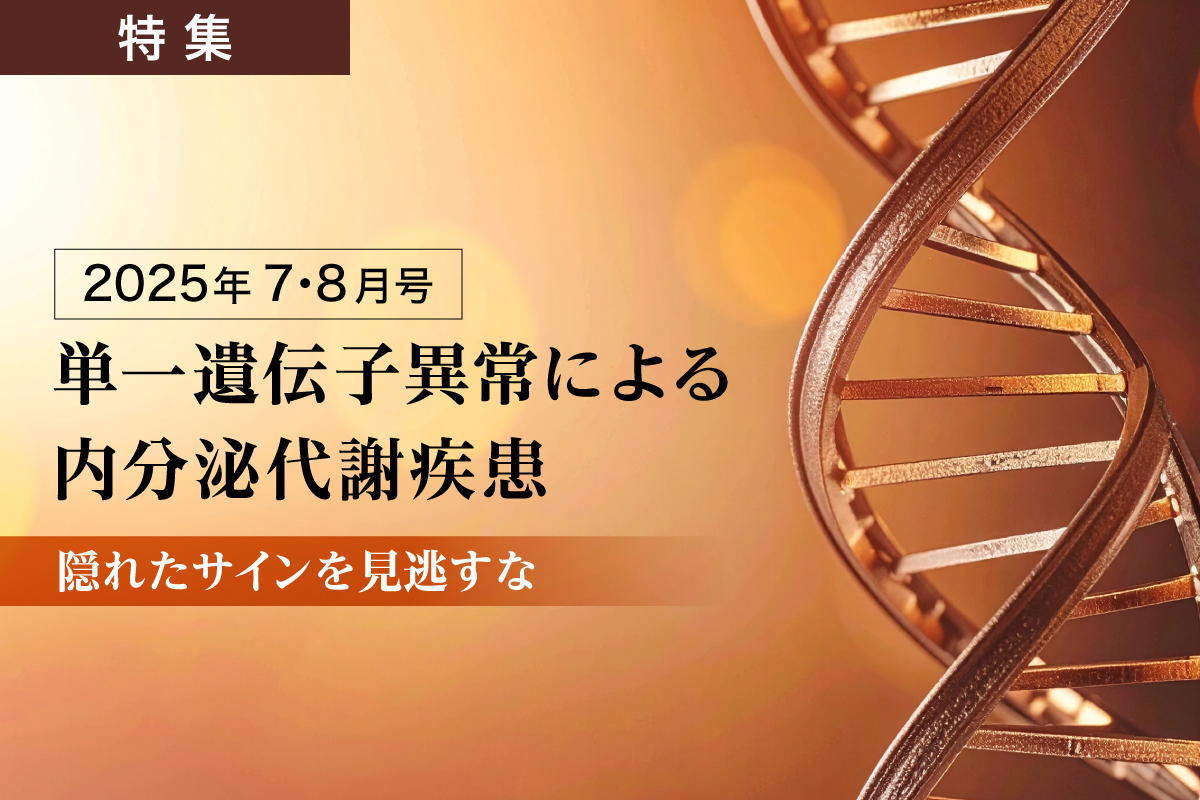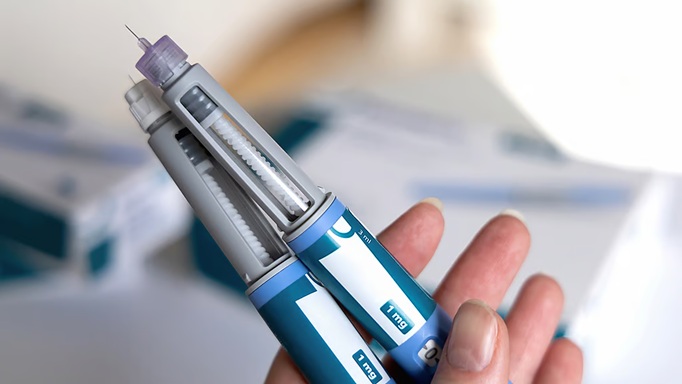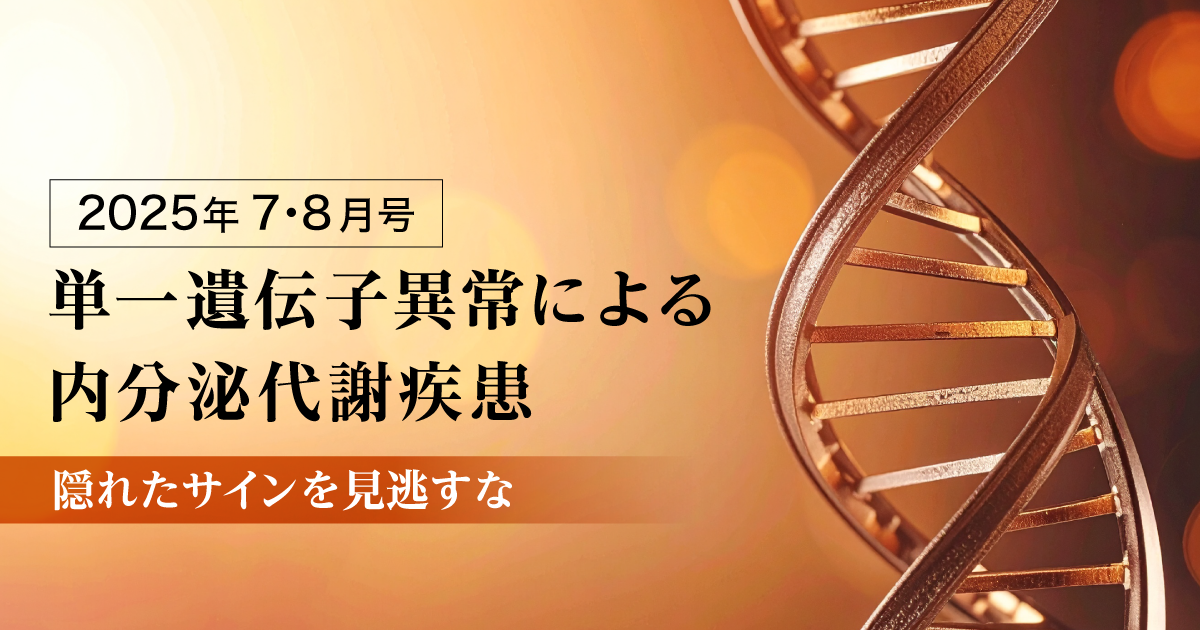免疫チェックポイント阻害薬による1型糖尿病発症 日本内分泌学会がガイドラインを発表 日本糖尿病学会が協力
2018.11.30
日本内分泌学会は、免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害(下垂体機能低下症、副腎皮質機能低下症、甲状腺機能異常症、副甲状腺機能低下症、1型糖尿病)の診療ガイドラインを発表した。1型糖尿病に関する部分は、日本糖尿病学会が協力し、共同で検討・作成した。

内分泌障害の発症を想定し、発症時に適切に対処することが重要
種々のがん治療に使用されている免疫チェックポイント阻害薬による、自己免疫反応と考えられる有害事象の発生が問題となっている。この内分泌障害は、進行がん患者の非特異的症状との鑑別が時に困難であり、また診断が遅れると重篤な転帰をたどることもあるため、治療に際しては発症を常に想定し、発症時には適切に対処することが求められる。 免疫チェックポイント阻害薬の使用は拡大している。日本では、抗CTLA-4抗体の「イピリムマブ(ヤーボイ)」が悪性黒色腫に、抗PD-1抗体の「ニボルマブ(オプジーボ)」が悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頸部がん、胃がんに、抗PD-1抗体の「ペムブロリズマブ(キイトルーダ)」が悪性黒色腫、非小細胞肺がん、尿路上皮がんに、抗PD-1抗体の「アベルマブ(バベンチオ)」がメルケル細胞がんに、抗PD-1抗体の「アテゾリズマブ(テセントリク)」が非小細胞肺がんにそれぞれ保険適用となっている。今後さらに新たな免疫チェックポイント阻害薬が承認される見込みだ。 そのため、日本内分泌学会は、免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害(下垂体機能低下症、副腎皮質機能低下症、甲状腺機能異常症、副甲状腺機能低下症、1型糖尿病)の診療ガイドラインを作成した。このうち、1型糖尿病に関しては日本糖尿病学会と共同で検討した。 同ガイドラインの1型糖尿病に関する部分は、同学会が2016年5月に公開をはじめた「免疫チェックポイント阻害薬使用患者における1型糖尿病の発症に関するRecommendation」を踏襲し、修正・加筆したもの。 免疫チェックポイント阻害薬による1型糖尿病発症は、抗CTLA-4抗体よりも、抗PD-1抗体による場合が多い。その頻度は1%未満だが、1型糖尿病は膵β細胞の機能廃絶が不可逆的であり、また急激に血糖が上昇し、適切な治療を行わなければ生命予後に影響すると、注意を喚起している。早期診断と早期のインスリン治療の開始が重要となる。 免疫チェックポイント阻害薬の投与開始前、および投与開始後来院日毎に、高血糖症状の有無を確認し、血糖値を測定することを求めている。また、1型糖尿病を発症した場合には、インスリン治療によって血糖コントロールが改善するまでは免疫チェックポイント阻害薬の休薬を検討することを推奨している。 免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害の診療ガイドライン(日本内分泌学会)免疫チェックポイント阻害薬に関連した1型糖尿病ことに劇症1型糖尿病の発症について(日本糖尿病学会) 関連情報
免疫チェックポイント分子LAG-3による免疫抑制メカニズムを解明 1型糖尿病発症のメカニズム解明と治療法開発に期待
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]