- トップページ
- 糖尿病医療 進歩の歴史
- 糖尿病医療 進歩の歴史 治療薬
糖尿病治療研究会 設立35周年記念事業
糖尿病医療 進歩の歴史 治療薬
治療薬の進歩
2021年
経口GLP-1受容体作動薬 セマグルチド 発売
2020年
初の経鼻グルカゴン製剤 発売
週1回のGLP-1受容体作動薬 セマグルチド 発売
“超”超速効型インスリン 発売
2018年
SGLT2阻害薬が1型糖尿病に保険適用
2015年
DPP-4阻害薬 トレラグリプチン 発売
SGLT2阻害薬 エンパグリフロジン 発売
DPP-4阻害薬 オマリグリプチン 発売
週1回のGLP-1受容体作動薬 デュラグルチド 発売
2014年
SGLT2阻害薬の適正使用の推奨
SGLT2阻害薬、5成分6製品が発売
糖尿病用薬で初のバイオシミラー発売
2013年
DPP-4阻害薬 サキサグリプチン 発売
週1回のGLP-1受容体作動薬 エキセナチド 発売
2012年
ビグアナイド薬の適正使用の推奨
DPP-4阻害薬 テネリグリプチン、アナグリプチン発売
2011年
DPP-4阻害薬 リナグリプチン 発売
速効型インスリン分泌促進薬 レパグリニド 発売
2010年
インスリンからGLP-1受容体作動薬への切替に注意喚起
インクレチン関連薬とSU薬併用の注意喚起
DPP-4阻害薬 アログリプチン 発売
DPP-4阻害薬 ビルダグリプチン 発売
GLP-1受容体作動薬、2製品が発売
2009年
DPP-4阻害薬 シタグリプチン 発売
2008年
インスリン販売名一部変更
2006年
α-グコシダーゼ阻害薬 ミグリトール 発売
2004年
ミチグリニド発売
インスリン グラルギンの発がん性に関する安全性情報
2003年
インスリン40単位製剤 出荷終了
2001年
インスリンアスパルト発売
インスリンリスプロ発売
2000年
グリメピリド発売
1999年
ナテグリニド発売
ピオグリタゾン発売
1997年
トログリタゾン発売
1994年
ボグリボース発売
1993年
アカルボース発売
1992年
エパルレスタット発売
1988年
ペン型インスリン注入器発売
1984年
グリクラジド発売
1980年
国内でプレプログラム型人工膵島開発
1978年
CSIIの開発
1975年
国内で人工膵島開発
1974年
人工膵島の開発
1973年
MCインスリン発売
1971年
グリベンクラミド発売
1969年
ブホルミン発売
クロルプロパミド発売
1968年
アセトヘキサミド発売
1965年
グリクロピラミド発売
1961年
メトホルミン発売
1957年
トルブタミド発売
1955年
メゾ蓚酸カルシウム発売
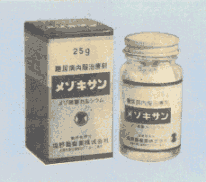
カルブタミド発売
1954年
フェンホルミン発売
1946年
NPH製剤開発
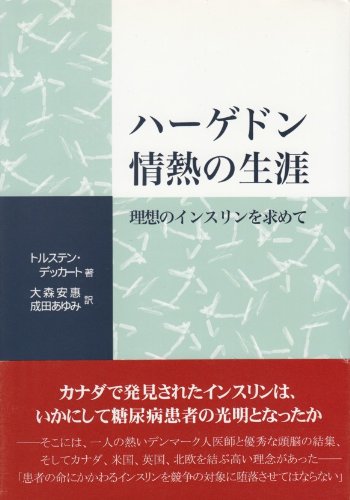
1940年
魚由来インスリン製剤化
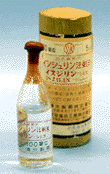
1936年
プロタミン亜鉛インスリン開発
1935年
国内初のインスリン製剤
1925年
インスリンの国際単位決定
1922年
インスリン製剤化
インスリン治療開始
テーマ別年表
全記録年表
医薬品・医療機器・検査機器
-
経口薬
-
注射薬
-
医療機器・検査機器
関連情報・資料
-
論考百選 -エキスパートたちの視点-
糖尿病医療の現場で活躍する専門家が、最新のトピック、医薬品・医療機器に関する情報、医療課題などをテーマに独自の視点で掘り下げて解説。 -
学会レポート
様々な学会を取材し、医療従事者の方々に今、特に知ってほしい演題を編集部が厳選。糖尿病に関係する話題はもちろん、医療トレンドとしても注目のテーマを簡潔レポート! -
慢性腎臓病とSDM~life goalsと療法選択~
年々増加傾向にある慢性腎臓病。糖尿病性腎症や慢性腎臓病の進展防止とともに、腎代替療法、さらにはSDMに焦点をあて、各分野のエキスパートが情報を提供。 -
糖尿病治療に役立つ情報をお届けするDexcom Express
Dexcomの新しいリアルタイムCGM G7の情報をはじめ、糖尿病治療に役立つ情報をアニメーションや動画で分かりやすく提供。【提供】デクスコムジャパン -
肥満症認知向上プログラム【セミナーレポート】
肥満症の基本から患者さんへのアプローチ、新ガイドラインを踏まえた診療、減量・代謝改善手術などの新たな治療選択肢などを紹介。【提供】ノボ ノルディスク ファーマ -
医療スタッフのギモンにこたえる グリコアルブミンQ&A
血糖管理指標である”グリコアルブミン”の基本から使い方まで、医療スタッフの皆さんの疑問にこたえるグリコアルブミンに関するQ&Aコーナー。【提供】ナガセダイアグノスティックス -
糖尿病ネットワーク
1996年より糖尿病に関する情報を発信する糖尿病患者さんと医療スタッフのための情報サイト。ニュースやイベント情報に加え、患者さんが交流できる掲示板が人気。 -
国際糖尿病支援基金
海外の団体と連携し、途上国の患者さんの支援活動を行っている基金。同じ病気を持つ仲間として何ができるかを考える。豊富な海外の糖尿病事情を紹介。



