医師のことばと糖尿病治療
~SDMを支えるコミュニケーション~
第1回患者と一緒に山をのぼる「治療同盟」という考え方

市立奈良病院 教育研修センター センター長
糖尿病・内分泌内科シニアアドバイザー
石井 均 先生
患者の心理を見極め、いかに治療意欲を高めるか—。石井均先生は、我が国の糖尿病治療において心理社会学的なアプローチの重要性をいち早く提唱し、「糖尿病医療学」として実践・普及に尽力されてきました。
本インタビュー連続2回の第1回目は、石井先生がどのような経緯からこの分野に注目することとなったのか、過去を振り返りながらSDM(Shared Decision Making:共同意思決定)の前提となる医師と患者の信頼関係についてお話しいただきます。
提供:株式会社ヴァンティブ メディカルアフェアズ部
“当事者の反応をケアする”ということ
患者と医療者間のコミュニケーションについて考えると、医療者には2つの役割があると言えます。第1は身体への科学的なアプローチであり、具体的には治療を行う、あるいは治療を止めること。第2は病気や治療に対する当事者の反応に対してケアすることです。
当事者の反応とは、患者さん自身が糖尿病と診断されたことをどうとらえているか。例えば、だるさや口喝のような自覚症状、提案された食事療法やインスリン導入をどう受け止めているか。糖尿病である自分を社会心理的にどう感じているか。最近注目されているスティグマの問題も含みます。
第1が薬や手術による治療であるとすれば、第2は、ことばやコミュニケーションによる治療です。これまでの糖尿病診療において、後者は軽く扱われてきました。コミュニケーションの重要性を理解されている先生方も、多忙な外来診療の現場ではなかなか実践できない場合が多いと聞いています。
がんの領域では2007年にがん対策基本法が施行され、「がん患者の意向を十分尊重したがん医療提供体制の整備」が掲げられました。法的な裏付けを機に、薬物療法や手術療法とともに、がんのつらさに対するメンタルケアの重要性への理解が広まり、コミュニケーションによる治療が組織的に行われています。がん領域の先生方はコミュニケーションの研修会もあり、ことばの重要性はよくご存じですが、それでも今の日本の医療の現状では十分に実践するのは難しく、むしろ外来診療が複雑化した現在では、以前より難しくなってきています。
しかし、コミュニケーションによる治療は医療の基本的役割であり、糖尿病をもつ人(person with diabetes:PwD。以下PwD)に治療を始める意欲、積極的な治療参加意欲をもってもらうためには極めて重要です。病気の経過や将来の見通しのみを伝えるような関わり方では心からの納得が得られず、適切な療養は行われません。
パターナリズム全盛の糖尿病医療のなかで
私は内分泌・糖尿病学が専門でしたが、コミュニケーションによる治療に関心をもったのは、40年ほど前、大学から市中病院への転勤がきっかけでした。内分泌疾患は適切な治療で治癒が見込めるので、医師の役割は正確な診断をし、治療法を選択することにありました。第1の役割、つまり身体的な治療が医師の役割の多くを占めていると言えます。
ところが、糖尿病ではそうはいきません。一部を除いて治癒は望めないので、悪化させず、併発症を予防することが治療目標になります。しかし、PwDにとって病院は病気を「治す」ところであり、「治る」ために通院している。私が最初に直面した困難は、PwDからの「糖尿病は治りますか?」という質問への回答法でした。「治らない」と言えば、PwDにとっては絶望でしかありません。とはいえ「血糖値が下がったら治る」と言えば、数値が安定したからと通院をやめかねません。
PwDはある種の希望をもちながら、治らないという絶望が隣り合わせにある。人間にとって、そんな曖昧で不確定な状態をもち続けるのは難しいことです。その状況とどう折り合いをつけ、無視せず、投げ出さず、ヤケにならずに病気と付き合い続けるのかー。私は、PwDひとりでは整理整頓が難しい状況を手伝い、支えることこそ医療者の役割だろうと考えました。
しかし、40年前の医療はパターナリズムの時代。日常診療でもパターナリズム的なアプローチがとられていました。医師は運動や食事、薬物治療の指導をしてPwDに「すべき」と伝え、その実践はPwDの持ち分とされつつも医師の指示に従うことが強く期待されていた。
「なぜやらないの?説明したでしょ?悪くなるのはあんただよ!」
熱心な医師がPwDを𠮟りつける医療に、私はだんだん切なくなっていきました。パターナリズムは父権主義や家父長主義などと訳されますが、今にして思えばそれは権力だった。しかしそんな厳しい指導をする医師自身は、よいことだと思って一生懸命やっているのです。「……先生も一度、自分でやってみたらわかるのに……」と言う人もいました。彼は受診時には自己血糖測定記録を白紙で持ってきて、待合室で適当に書く。当然HbA1cと合わないのでまた医師から怒られる。毎日のようにそんなことがありました。私はそういう診療が面白くなく、もっとPwDも医療者も気持ちよくやれる糖尿病医療がないものかと悩みました。
「糖尿病の研究は進んでいるけれども、残念ながら今はまだ治せない。でも、今ある治療法をうまく使ってもらえるなら、糖尿病をもたない人と同じような人生を歩むことは可能です。私はあなたにその方法を教え、助言することはできますが、実際やるのはあなた自身。あなたが一緒に治療に取り組もうという気持ちになってもらえるとよいのですが」
そんなふうに、治せないという現実に謙虚に向き合いながら、医療者とPwDがともに歩む医療があるべきではないかと考えていました。そしてPwDのセルフマネジメントや行動変容を専門的に学べる施設はないかと探しているうちに、私は米国ジョスリン糖尿病センターのメンタルヘルスユニットでPwDへの行動支援と心理的アプローチを先駆的に行なっていることを知り、「これしかない!」と憑かれたように渡米したのです。

海外留学で学んだ「治療同盟」という考え方
私がジョスリン糖尿病センターに留学したのは、1993年のこと。マサチューセッツ州ボストンにあるこのセンターは、糖尿病専門病院として米国で最も伝統のある施設で、1型糖尿病に対するインスリン治療をその創世期(1922年)から実施した病院です。メンタルヘルス部門は1980年代に作られ、独自の診療とともに、他部門と協力して糖尿病ケアを支えていました。
直属の上司だったアラン・ジェイコブソン博士(Alan M. Jacobson, M.D.)は、精神分析の専門家です。彼の下で糖尿病治療の過程における「うつ」の治療や、認知行動心理学を用いたPwDの行動変容のためのケアが行われていました。様々なアプローチ法があるなか、共通する理念として「人間の行動を他人が力ずくで変えることはできない」と語られていたことが強く印象に残りました。
事例検討会では、私が「このPwDはどうしても食べたいという気持ちが抑えられないので困っている」と話したところ、「それは当然でしょう」と一笑に付されました。「糖尿病になったからといって、急に食べたくなくなるといったことはない。『食べたいという気持ち』と『血糖管理の重要性』との折り合いをつけていくことが大切で、一方的に医療者がやめろと言ってやめるものではない。血糖値とインスリンの変動を見比べて他の代替案をPwD自身が自分で工夫して見つける。手助けしながらそれを待つのが我々の役割だ」と言われたのは、まさに目からウロコでした。
PwDの話を聞き、うまく行ったことは評価し、うまく行かなかったことは別の方法を一緒に考える。PwDと医療者が同じ方向に向かって助け合いながら一緒に山をのぼっていく。ジェイコブソン博士はそれを「治療同盟(therapeutic alliance)」と呼びました。「関係づくりが、PwDの心と行動を支える基礎となる」という考え方に、私は意を強くしました。
帰国する私にジェイコブソン博士は、「日本であなたの仲間を見つけ、運動(アクション)を起こしなさい」とエールを送ってくれました。心理社会的領域では世界最先端の米国でも、彼らは米国糖尿病学会で重要な一部門として認めてもらうために、長く大変な努力を重ねてきていたのです。
帰国後、私はPwDの治療意欲を高めるための心理社会的領域の確立に励み、注力しました。嬉しいことに糖尿病臨床に悩んでおられる先生方ほどこの取り組みへの評価の度合いが高く、本領域の広がりは当初の私の予想をはるかに超えるものになっていきました。(2回目に続く)
参考文献
- 石井均「糖尿病医療学入門」(2011年/医学書院)
市立奈良病院 教育研修センター センター長、糖尿病・内分泌内科シニアアドバイザー
石井 均(いしい ひとし)
1976年京都大学医学部卒業後、同大学院医学研究科博士課程修了。天理よろづ相談所病院内分泌内科を経て、1993年に米国のジョスリン糖尿病センターに留学。アラン・ジェイコブソン氏、ウィリアム・ポランスキー氏らから「糖尿病の心理・社会的領域」を学び、帰国後、糖尿病患者への心理的アプローチに取り組む。天理よろづ相談所病院副院長兼内分泌内科部長、奈良県立医科大学糖尿病学講座教授、同大学医師患者関係学講座教授を経て現職。臨床心理に基づく糖尿病治療の第一人者。『医療現場の共感力』『病を引き受けられない人々のケア』 『糖尿病医療学入門』『糖尿病エンパワーメント』他著書多数。
提供:株式会社ヴァンティブ メディカルアフェアズ部

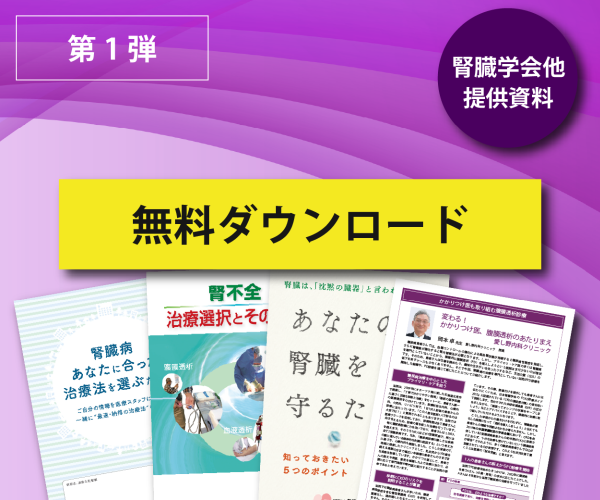

 資料請求はこちら
資料請求はこちら