第21回 インスリン製剤 (4)
2016.01.15
今回は基礎インスリンの重要性とそれを補充する製剤の特徴についてお話しします。
インスリンを始めたのだから良い血糖コントロールになって当然、と考える患者さんがほとんどですが、改善が途中で止まる方も多いのが実情です。これは第1に理想的な基礎分泌を、生体の状況に応じて安定して供給出来るインスリンがないこと。第2にインスリンが皮下投与のため、門脈内に分泌される生体の内因性インスリンには太刀打ち出来ないことがあげられます。
今回は基礎インスリンの重要性とそれを補充する製剤の特徴についてお話しします。
インスリンを始めたのだから良い血糖コントロールになって当然、と考える患者さんがほとんどですが、改善が途中で止まる方も多いのが実情です。これは第1に理想的な基礎分泌を、生体の状況に応じて安定して供給出来るインスリンがないこと。第2にインスリンが皮下投与のため、門脈内に分泌される生体の内因性インスリンには太刀打ち出来ないことがあげられます。
 糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
毎号、明日の臨床に役立つ時宜を捉えたテーマを取り上げ、各分野のエキスパートが徹底解説。
専門医の先生はもちろんのこと、これから専門医を目指される先生まで、ぜひアップデートにお役立てください。

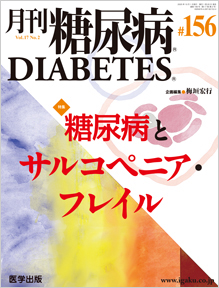







当サイトは、糖尿病に関連した薬剤や医療機器の情報を
医療関係者の方に提供するサイトです。
該当する職種をクリックして中へお進みください。