日本糖尿病協会の出発
2015.09.03
1. 糖尿病教室がはじまる
1950年以後は糖尿病患者が次第に増加し、糖尿病を得意とする大学病院や大都会の病院では、糖尿病の診療日をきめて血糖検査をすることがはじまった。当時は中央検査部がなく血糖検査はすべて担当医師が耳朶から血液0.1mlをハーゲドロンピペットで吸い取り、それから最短40分かかって測定していた時代であった(本シリーズ No.1 参照)。
1950年以後は糖尿病患者が次第に増加し、糖尿病を得意とする大学病院や大都会の病院では、糖尿病の診療日をきめて血糖検査をすることがはじまった。当時は中央検査部がなく血糖検査はすべて担当医師が耳朶から血液0.1mlをハーゲドロンピペットで吸い取り、それから最短40分かかって測定していた時代であった(本シリーズ No.1 参照)。
 糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
毎号、明日の臨床に役立つ時宜を捉えたテーマを取り上げ、各分野のエキスパートが徹底解説。
専門医の先生はもちろんのこと、これから専門医を目指される先生まで、ぜひアップデートにお役立てください。

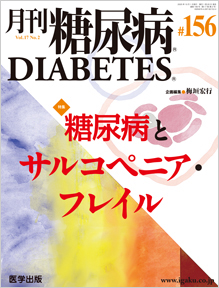







当サイトは、糖尿病に関連した薬剤や医療機器の情報を
医療関係者の方に提供するサイトです。
該当する職種をクリックして中へお進みください。