運動療法のピットホール -早期腎症を視野に入れて-
2006.10.15
運動療法のメリットとデメリット
運動療法が2型糖尿病の治療に有用であることは、言うまでもありません。また近年注目されているメタボリックシンドロームに対する対処法としても、その病態の基盤である内臓脂肪型肥満の解消に、運動療法の効用が強調されています。
運動療法が2型糖尿病の治療に有用であることは、言うまでもありません。また近年注目されているメタボリックシンドロームに対する対処法としても、その病態の基盤である内臓脂肪型肥満の解消に、運動療法の効用が強調されています。
 糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
毎号、明日の臨床に役立つ時宜を捉えたテーマを取り上げ、各分野のエキスパートが徹底解説。
専門医の先生はもちろんのこと、これから専門医を目指される先生まで、ぜひアップデートにお役立てください。




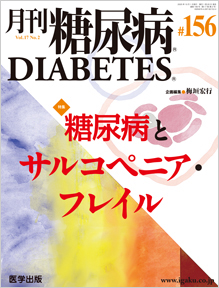




当サイトは、糖尿病に関連した薬剤や医療機器の情報を
医療関係者の方に提供するサイトです。
該当する職種をクリックして中へお進みください。