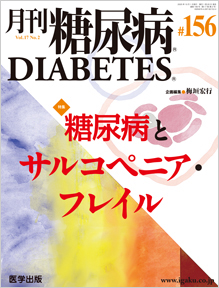第30回 高齢者糖尿病診療の特徴と注意点(4)
2018.04.16
はじめに
前回は【A群】「血糖変動幅を減少させる薬剤」を高齢者に使用する際の注意点でしたが、今回は【B群】「空腹時血糖が下がり1日の平均血糖を改善する薬剤」のSU薬、ビグアナイド薬、チアゾリジン薬を取り上げます。この中でSU薬は低血糖の元凶とされ「SU薬の時代は終わった」とある講演で聞きましたが本当にそうでしょうか? 当院では少量のSU薬をやめると、驚くほど血糖値が悪くなる治療歴の長い高齢糖尿病患者さんがいます。また高齢で経済的に厳しい方は予想以上にいらっしゃり、安価で有効例も多いSU薬は無視できません。「少量のSU薬は基礎インスリン」との感覚で使用 するのが良いと思います。SU薬を安全に使いこなすのは糖尿病診療をする実地医家の腕の見せ所でしょう。