第10回 SGLT2阻害薬(1)
2013.04.15
今回は近い将来、新薬ラッシュとなりそうなSGLT2阻害薬についてです。私が駆け出しの医者の頃、「血糖がそれほど高くないうちに尿中にブドウ糖を捨てられたら」というアイデアを話した時は取り合ってもらえなかったのを思い出します。それが現実になろうとしている訳で、医学・薬学の進歩は感慨深いものがあります。
今回は近い将来、新薬ラッシュとなりそうなSGLT2阻害薬についてです。私が駆け出しの医者の頃、「血糖がそれほど高くないうちに尿中にブドウ糖を捨てられたら」というアイデアを話した時は取り合ってもらえなかったのを思い出します。それが現実になろうとしている訳で、医学・薬学の進歩は感慨深いものがあります。
 糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
糖尿病・内分泌プラクティスWeb
糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル
毎号、明日の臨床に役立つ時宜を捉えたテーマを取り上げ、各分野のエキスパートが徹底解説。
専門医の先生はもちろんのこと、これから専門医を目指される先生まで、ぜひアップデートにお役立てください。

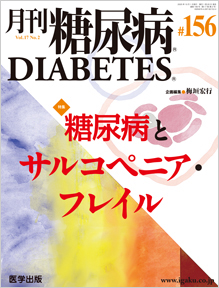







当サイトは、糖尿病に関連した薬剤や医療機器の情報を
医療関係者の方に提供するサイトです。
該当する職種をクリックして中へお進みください。