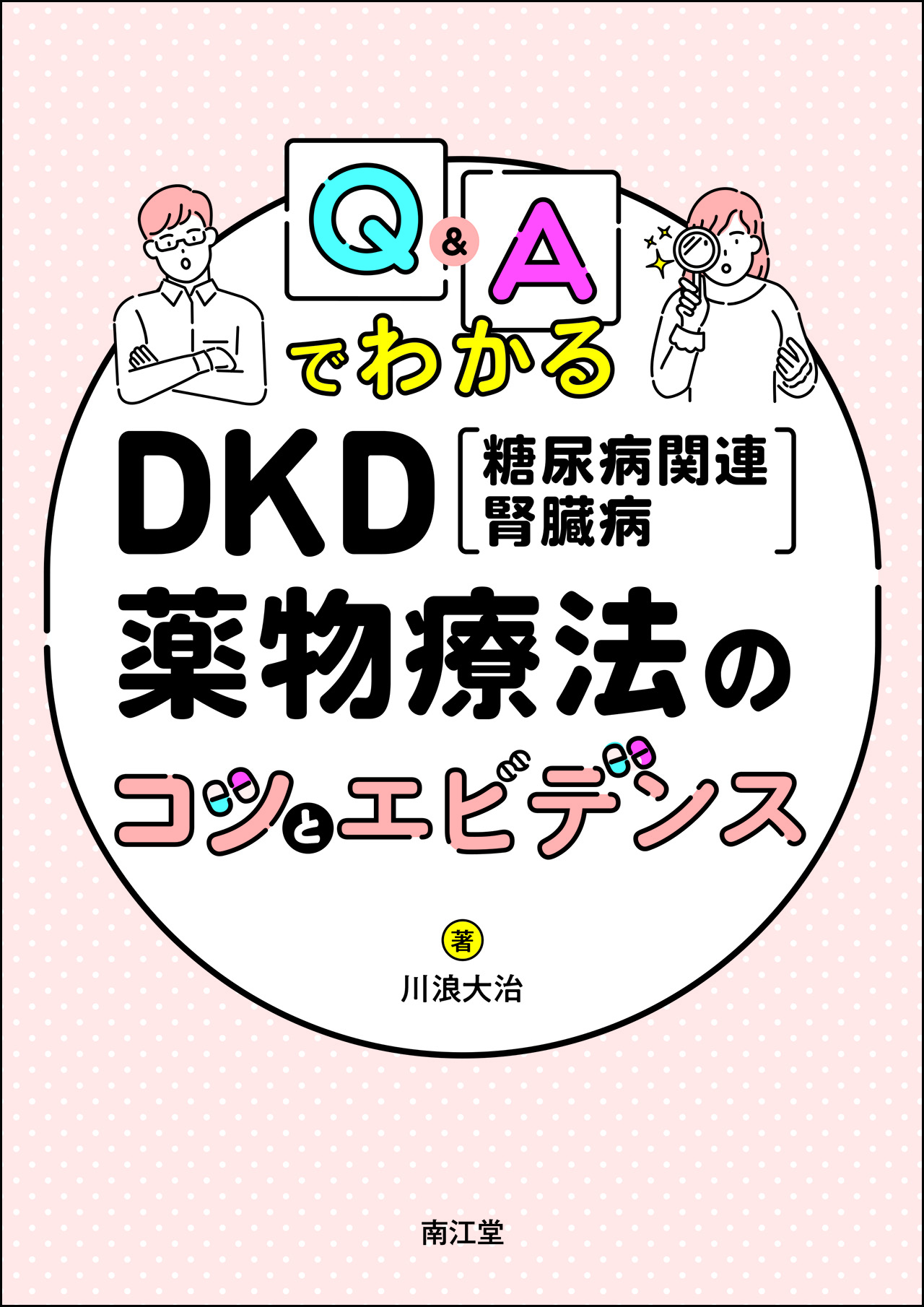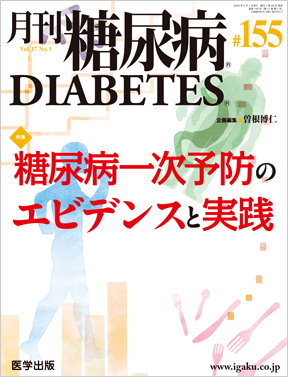輸入が途絶えて魚インスリンが製品化
2014.03.15
1. 戦争で2型は消え1型は残った
普仏戦争や第1次大戦で、戦争になると食糧不足で糖尿病の滅少することが経験されていたが、わが国では太平洋戦争でそれがはっきりと現れた。乏しい食糧の配給で戦争末期には1日平均1,900kcalで我慢させられたので、糖尿病がよくなったのはよかったが、一方栄養失調症もみられるようになった(図1)。戦争浮腫として知られていた低蛋白血症による全身の浮腫などである。糖尿病の研究者は糖尿病がいなくなったので栄養失調の研究をしたわけである。京府医大飯塚直彦教授(秋田県出身)もその1人で栄養失調が終戦直後からその翌年に多くなったことを報告している。