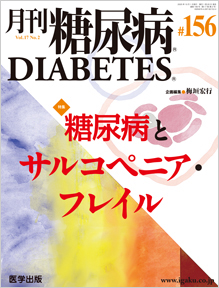新たな糖尿病合併症ターゲット ~認知症と心不全~
2020.05.13
高齢者糖尿病の治療がかわる
糖尿病合併症は、三大合併症といわれる網膜症、神経障害、腎症の細小血管障害および脳血管、冠動脈、下肢の動脈硬化性疾患ですが、様々な糖尿病治療薬の登場や糖尿病に対する取り組み、糖尿病のみならず医学全般のレベル向上もあり糖尿病患者の予後は改善してきました。その結果糖尿病患者は高齢化し、サルコペニア、フレイル、ポリファーマシーなどの問題がでてきており、糖尿病の診療は新たな局面を迎えています。多くの糖尿病患者が高齢化しているため、ここではあえて高齢者糖尿病と断らず解説します。
今までは血糖値を下げることを中心に考えてきた糖尿病治療は、①低血糖を起こさない②栄養を低下させない③可能な限り少ない薬剤での血糖コントロールが求められるようになりました。そのため目標とする血糖指標も緩和され、サルコペニアを意識した食事摂取量に対する見直しも始まりました。