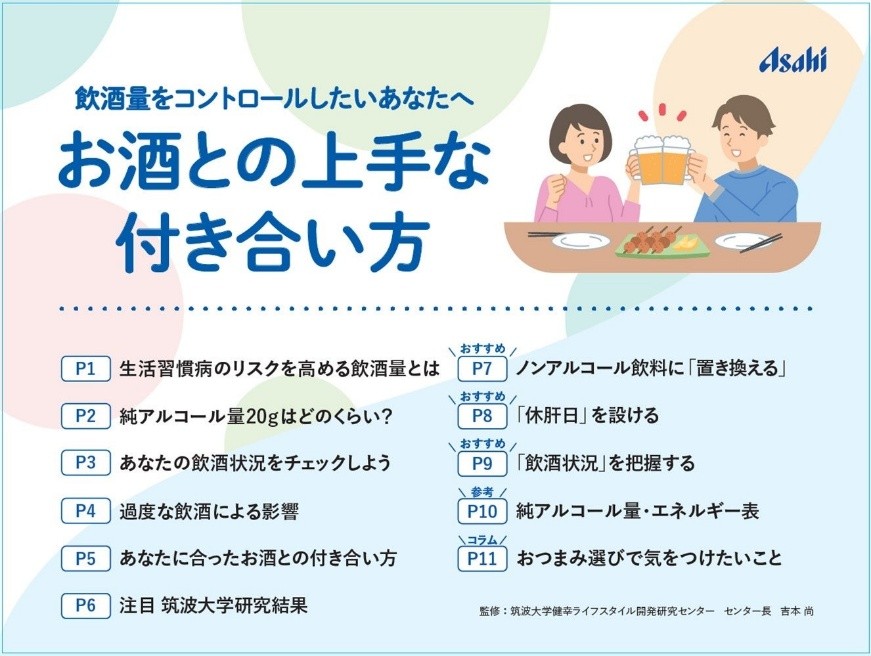中年期に高血糖でも適切に管理すれば循環器病リスクは低下 国立循環器病研究センター
2019.02.22
国立循環器病研究センター(国循)は、長期にわたる空腹時血糖の推移と循環器病発症の関連を明らかにしたと発表した。
年齢とともに血糖値が上昇することで循環器病リスクは高まるが、中年期に適切にコントロールすれば発症を抑制できることが示唆された。
年齢とともに血糖値が上昇することで循環器病リスクは高まるが、中年期に適切にコントロールすれば発症を抑制できることが示唆された。

空腹時血糖値の長期的な推移と中年以降の循環器病発症リスクの関係を明らかに
研究は、国循予防健診部の宮本恵宏部長、尾形宗士郎研究員(現・藤田医科大学講師)らの研究グループによるもで、詳細は米国心臓協会の専門誌「Journal of American Heart Association」に掲載された。 高血糖が冠動脈疾患と脳卒中のリスク(循環器病リスク)であることを多くの研究が報告しているが、これらは特定の1時点もしくは2~3時点といった少ない回数の血糖値の平均値を評価している。一方で、臨床では同一患者から数年にわたり複数回血糖値を測定し、その推移から血糖値を評価して治療を進める。このため、臨床と同様に経時変化から循環器病発症リスクを推定できる研究が必要とされている。 そこで研究グループは、国循が1989年から実施している都市部住民を対象としたコホート研究「吹田研究」において、1989~2013年の期間での循環器病発症の有無と空腹時血糖値の関係を解析した。解析対象者は男性3,120名、女性3,482名だった。 空腹時血糖値を2年おきに測定し、「joint latent class mixed model」という統計モデルを用いて、空腹時血糖値推移の経時変化パターン分類を行った。この解析モデルは、変数(空腹時血糖値)の経時的変化を統計的にクラス分類して、それぞれのクラス分類集団の生存率(循環器病発症率)を求めるもの。 その結果、観察期間中に初めて冠動脈疾患あるいは脳卒中を起こしたのは、男性356名(追跡期間中央値17.2年)、女性243名(同20.2年)だった。解析したところ、男性で3パターン、女性で2パターンが同定された。 男性のうち、加齢とともに空腹時血糖値が大きく上昇するグループでは循環器病累積発症率が高い一方で、中年時に血糖値が高くてもその後適切にコントロールできたグループでは発症率が低くなった。女性では、空腹時血糖値が大きく上昇するグループは上昇幅が少ないグループと比較して、循環器病累積発症率がやや高くなった。 これらの解析から、「年齢とともに血糖値が上昇することで循環器病リスクが高まる」という過去の研究と同様の結果が導き出せた一方で、「中年期に血糖値を適切にコントロールできれば循環器病の発症を抑制できる」ことも示唆された。 なお、研究グループは「今回の研究は観察研究であり、確定的な結論を出すことはできない。今後は介入研究など因果関係を検討する研究が必要」と述べている。
男性における空腹時血糖値の推移パターンと、そのパターン内における循環器病累積発症率
左図の縦軸は空腹時血糖値を、横軸は年齢を、図中の線は統計モデルによる推定値(真ん中の線)とその95%信頼区間(上と下の線で囲まれた区間)を示している。
右図の縦軸は循環器病累積発症率を、横軸は年齢を、図中の線は統計モデルによる推定値を示している。


国立循環器病研究センター
(1)中年期の血糖値は高いがその後適切にコントロールされた群(class1:黒)、(2)中年期から血糖値が緩やかに上昇する群(class2:赤)、(3)中年期から老年期に血糖値が急上昇する群(class3:緑)の循環器病累積発症率は、class3では過去の研究と同様に増加するが、class1ではclass2よりも発症が抑えられていた。
女性における空腹時血糖値の推移パターンと、そのパターン内における循環器病累計発症率 左図の縦軸は空腹時血糖値を、横軸は年齢を、図中の線は統計モデルによる推定値(真ん中の線)とその95%信頼区間(上と下の線で囲まれた区間)を示している。 右図の縦軸は循環器病累積発症率を、横軸は年齢を、図中の線は統計モデルによる推定値を示している。

中年期から老年期にかけて血糖値が大きく上昇する群(class1:黒)はゆるやかに上昇する群(class2:赤)と比較してやや循環器病発症率が高くなる。
Longitudinal Trajectories of Fasting Plasma Glucose and Risks of Cardiovascular Diseases in Middle Age to Elderly People Within the General Japanese Population: The Suita Study(Journal of American Heart Association 2019年1月28日)
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]