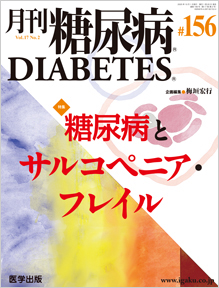第28回 高齢者糖尿病診療の特徴と注意点(2)
2017.10.16
はじめに
高齢者の糖尿病治療において何が一番難しいかと言えば、それは不測の低血糖という厄介なものへの対応です。これは網膜症の悪化を招いたり、転倒・骨折、認知症、そして心血管病などいわゆる「老年病」の引き金にもなるので重要です。
HbA1cが高いから低血糖は来さない、と安心していると足をすくわれます。外来で「いつも血糖測定値が高い時が多いのにHbA1cは優秀ですね!」というやり取り、何かが変だと思われませんか?貧血でHbA1cが低く出ているわけではない症例です。実はこのような例の多くは「無自覚性の夜間低血糖!」を示している可能性が高いということに思いを馳せる必要があります。このことは最近の持続血糖測定器の進歩で明らかになっています。今回は高齢者の糖尿病治療を、不測の低血糖を踏まえての安全面から考えてみたいと思います。