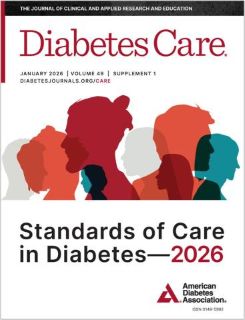「スタチン」「フィブラート」併用の原則禁忌が解除 腎機能低下患者でも両剤の併用が可能に
2018.10.20
厚生労働省は、高脂血症用薬のスタチンとフィブラートの併用について、腎機能の臨床検査値に異常が認められる患者については、「原則禁忌」から削除し「重要な基本的注意」とする添付文書の改訂を行うよう指示した。

「原則禁忌」から「重要な基本的注意」に改訂
厚労省医薬・生活衛生局医薬安全対策課は2018年10月16日、腎機能の臨床検査値に異常が認められる患者に対するスタチンとフィブラートの併用について、添付文書上の「原則禁忌」から削除するよう日本製薬団体連合会に通知で指示した。 「原則併用禁忌」の項の「フィブラート系薬剤(ベザフィブラート等)」を削除すると同時に、「基本的な注意事項」に下記を追記した。
「腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状(筋肉痛、脱力感)の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。」
両剤の併用について、欧米では原則禁忌の制限なくスタチンとフィブラートが併用されており、国内においても併用治療のニーズがあることなどから、日本動脈硬化学会が2018年4月に、併用に関する添付文書改訂の要望書を厚労省に提出していた。
これを受け、厚労省は医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対し、腎機能低下患者におけるスタチンとフィブラート併用時の安全性について調査を依頼。その結果、腎機能に関する臨床検査値に異常が認められ、かつ、スタチンとフィブラートを併用した症例は、製造販売後調査及び国内副作用報告において少なく、安全性に関する情報は限定的だった。
調査結果について専門委員から、(1)スタチンだけでは、リスクコントロールができない症例があるため、フィブラートの併用を必要とする症例が一定の割合で存在する。副作用より、薬剤の有用性が期待される症例がいる、
(2)スタチンとフィブラートとの併用について、横紋筋融解症に関する注意喚起を継続して行うのであれば、「原則禁忌」及び「原則併用禁忌」を削除することは妥当と考えられる、
(3)「原則禁忌」及び「原則併用禁忌」が削除されることにより、腎機能に異常のある患者にもスタチンとフィブラートの併用が安易に行われることを懸念している。腎機能に異常のある患者での併用時における注意喚起を継続して行うことが重要である、
――といった意見が出されていた。 「使用上の注意」の改訂について(厚生労働省 2018年10月16日)
使用上の注意の改訂指示通知(2018年10月16日)(医薬品医療機器総合機構)
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]