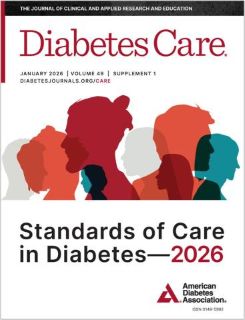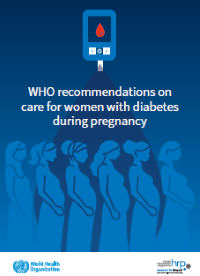メトホルミンの禁忌は重度の腎機能障害患者(eGFR30未満)のみに 厚労省が安全性情報
2019.08.13
厚生労働省は8月6日に「医薬品・医療機器等安全性情報 365号」を公表し、メトホルミンの禁忌「腎機能障害」等の見直しの検討を行った結果、
使用上の注意の改訂による注意喚起を行うよう指示したことを明らかにした。

重度の「腎機能障害」のみ禁忌
脱水やアルコール摂取への注意を喚起
メトホルミンは、乳酸アシドーシスのリスクがあり、特に腎機能障害患者ではメトホルミンの排泄が遅延し血中濃度が上昇し、乳酸アシドーシスのリスクがさらに高まることが懸念されたため、腎機能障害患者には禁忌となっていた。
今回の注意喚起は、2019年5月31日に開催された令和元年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(安全対策調査会)での検討をふまえたもの。
ビグアナイド系薬剤であるフェンホルミンによる重篤な乳酸アシドーシスの副作用が報告されて以来、国内および海外で同じくビグアナイド系薬剤であるメトホルミンの添付文書にて乳酸アシドーシスに関連する注意が喚起されており、腎機能障害患者については、腎機能の程度に応じて使用が制限されている。
日本糖尿病学会の「メトホルミンの適正使用に関するRecommendation」では、腎機能をeGFRで評価し、30mL/min/1.73m²未満は禁忌、30~45mL/min/1.73m²は慎重投与することが示されている。
一方で、腎機能障害患者におけるメトホルミンの安全性について、海外の添付文書が改訂され、軽度から中等度の腎機能障害患者でもメトホルミンを用いた場合は、薬物濃度はおおむね治療範囲内にとどまり乳酸濃度は大幅に上昇しないことや、乳酸アシドーシスの発現リスクは製剤により違いがないことなどが示された。
これらを受けて安全対策調査会は、日本糖尿病学会の賛同を得て、メトホルミン含有製剤の添付文書における、腎機能障害患者および乳酸アシドーシスに関する注意喚起についての見直しを検討した。
国内で販売されているメトホルミン塩酸塩は、メトグルコ錠250mg、500mg(大日本住友製薬)、グリコラン錠250mg(日本新薬)などがある。1日最高用量は、メトグルコ錠では2,250mg、グリコラン錠では750mg。腎機能障害患者については、高投与製剤は中等度以上の患者が、低投与量製剤は軽度から重度の患者が、それぞれ禁忌とされている。
メトホルミンは腎排泄型の薬剤であり、メトホルミンの血中濃度は、腎機能障害の程度に応じて高くなる。減量により、中等度腎機能障害患者におけるメトホルミンの血中濃度を腎機能正常患者と同程度に低減可能だ。
日本で報告された乳酸アシドーシスの副作用347例のうち、中等度の腎機能障害患者(eGFR30~60 mL/min/1.73m²)43例の大半は、腎機能以外のリスク因子(脱水、心血管系疾患など)が認められている。
これらの調査結果をふまえ、メトホルミン含有製剤の添付文書について、以下の改訂が了承された――。
(1) 腎機能障害患者への投与については、リスク最小化(少量からの投与開始、患者の状態に応じた用量調整、慎重な経過観察等)を行った上で、禁忌は重度の腎機能障害患者(eGFR<30)のみとする。腎機能評価については、欧米の添付文書、日本糖尿病学会のReccomedationで、eGFRによる評価が推奨されていることをふまえ、これにもとづく記載に変更する。
(2) eGFRにもとづき腎機能障害患者に係るメトホルミン塩酸塩としての1日最高用量の目安を記載する。
今回の改訂により、メトホルミンの低投与量製剤と高投与量製剤の禁忌はともに、重度の腎機能障害患者(eGFR<30)のみとなり、軽度から中等度の腎機能障害患者に投与できるようになった。
しかし、軽度から中等度の腎機能障害患者にメトホルミンを投与する場合には、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸アシドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、慎重に投与する必要がある。
厚労省では「とくに、中等度の腎機能障害患者にメトホルミンを使用する場合には、投与は少量から開始し、投与中はより頻回に腎機能(eGFR)を確認するなど慎重に経過を確認し、投与の適否や用量の調節を検討してください。増量する場合は、1日最高用量の目安も参考に、効果を確認しながら徐々に増量してください。また、腎機能障害の有無にかかわらず、食欲不振等の経口摂取不良による脱水や過度のアルコール摂取等で、患者の状態が急変し乳酸アシドーシスを発現した副作用症例が報告されていますので、乳酸アシドーシスの予防、初期症状、初期対応に関する患者教育も十分に行っていただくようお願いいたします」と注意喚起している。
2019年度 医薬品・医療機器等安全性情報(医薬品医療機器総合機構)
腎機能障害患者におけるメトホルミン塩酸塩の一日最高用量の目安
(3) 腎機能障害以外のリスク因子、経口摂取が困難な場合などの脱水のリスクや、過度のアルコール摂取には特に注意が必要である旨を追加するとともに、その他乳酸アシドーシスに関連する注意を整理する。
(4) 低投与量製剤と高投与量製剤の乳酸アシドーシスに関する注意喚起の差異を是正する。
| eGFR (mL/min/1.73m²) | 目安量 |
| 60≦eGFR<90 | 2,250mg |
| 45≦eGFR<60 | 1,500mg |
| 30≦eGFR<45 | 750mg |
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]