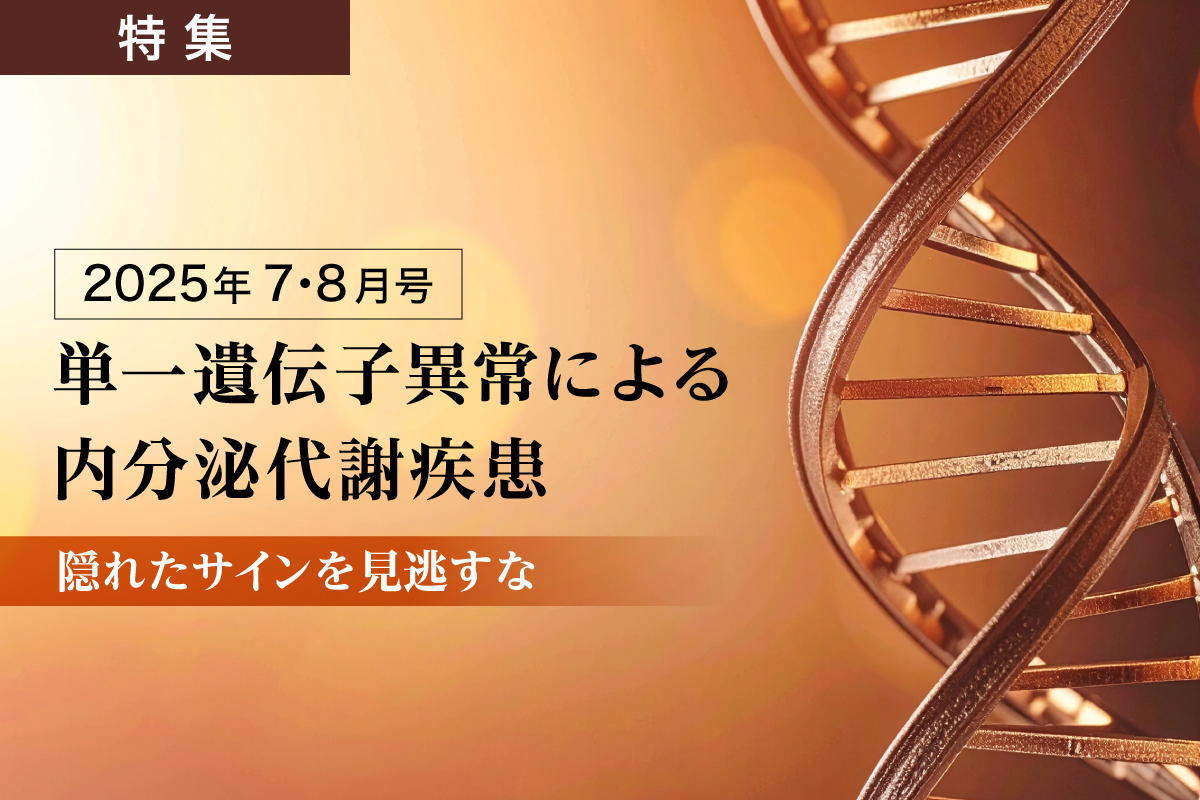インスリン作用研究の最新の知見 インスリン抵抗性の機序を解明
2013.05.23
第56回日本糖尿病学会年次学術集会
インスリン作用の研究は、糖尿病治療の要として重要な位置を占めている。第56回日本糖尿病学会年次学術集会(5月16~18日、熊本市)の特別シンポジウム「インスリン作用研究の進化と展望」では、1980年代以降の研究の発展をふまえ、最新の知見について発表された。
インスリン作用の研究は、糖尿病治療の要として重要な位置を占めている。第56回日本糖尿病学会年次学術集会(5月16~18日、熊本市)の特別シンポジウム「インスリン作用研究の進化と展望」では、1980年代以降の研究の発展をふまえ、最新の知見について発表された。

基調講演で春日雅人氏(国立国際医療研究センター)は、80年代以降のインスリン受容体(IR)分子の構造解明と機能の解明の道程を解説した。 インスリン作用の第一歩は、インスリン分子の細胞膜上に存在する特異的受容体への結合である。この結合により、インスリン受容体に内在するチロシンキナーゼが活性化され、基質蛋白のチロシン残基を燐酸化する。この基質蛋白の代表的なものとしてIRS(インスリン受容体基質)が同定される。IRSのチロシン残基が燐酸化されると、Grb2/Sos複合体、PI3Kが結合し活性化される。これらのうち、インスリンの代謝作用のほとんどはPI3Kを介して伝達されていると考えられている。 現在では組織・臓器特異的遺伝子欠損マウスを作成する技術が普及しつつあり、インスリン作用機序の多くの部分が解明されつつあ。今後はインスリン作用をよりミクロの視点から解析する方向と、マクロの視点から解析する方向の研究が求められているという。 湯浅智之氏(徳島大学)らは、IRの細胞外領域が血中に遊離し可溶化していることを発見し、その後、詳細な機序を研究している。可溶性インスリン受容体(sIR)と名付けられた因子は、血中においてインスリンと結合し、糖尿病におけるインスリン抵抗性に関与する可能性がある。 湯浅氏らはこれまでにもELISAを用いてsIR放出メカニズムの解析を行ってきたが、細胞から放出されるsIRはELISAの検出限界濃度とほとんど変わらず、正確な解析ができなかった。そこで同じ抗体を用いながら100~1,000倍程度に超高感度化する超高感度ELISAを用いて、培養細胞におけるsIR放出の解析を行った。 窪田直人氏(東京大学)はIRS-1およびIRS-2の病態生理的役割について講演。血管内皮細胞に発現するIRS-2がインスリンによる毛細血管拡張に関与し、間質へのインスリン移行および骨格筋での糖取り込みの調節を介してインスリン抵抗性に関わるという。2型糖尿病では血管内皮細胞のIRS-2が低下し骨格筋での糖取り込みが低下することもあきらかにした。 2型糖尿病では肝臓で糖代謝においてインスリン抵抗性を呈するのに対し、脂質代謝ではむしろインスリン作用の亢進が認められるのは、高インスリン血症によって発現量が低下するIRS-2を介する糖新生抑制は障害されるが、発現量が低下しないIRS-2を介する脂肪合成はむしろ促進することで説明できるという。 植木浩二郎氏(東京大学)はIRSとの結合によりシグナルを伝達するPI3Kについて解説した。PI3Kはグルコース取り込み、グリコーゲン合成、蛋白合成、糖新生の抑制、脂肪分解の抑制、脂肪酸の合成などの代謝作用に加えて、抗アポトーシスの作用や増殖作用などのインスリン作用を媒介する鍵分子であることがあきらかになっている。 インスリンの分泌が低下することが膵β細胞のインスリンシグナルを低下させ、このことがますますインスリンの分泌を減弱させる、という悪循環にあるために病態の増悪をきたしていると考えられ、PI3Kを標的とした治療がこの悪循環を断ち切る可能性のあることをあきらかにした。 中江淳氏(慶應義塾大学)は、インスリン作用に関連するさまざまな遺伝子を調節するFOXO1の研究を紹介した。FOXO1は、インスリン刺激により、PI3k/Akt依存性にリン酸化され、核内より核外へ転出されることによりその転写活性が抑制される転写因子。摂食調節やエネルギー代謝調節はFOXO1を中心に説明できるという。インスリン抵抗性に関しては、マクロファージに発現するFOXO1が炎症惹起に関与することを解説した。 松本道宏氏(国立国際医療研究センター研究所)は、遺伝子発現を調節するタンパク質であるCITED2が、ホルモンによる肝臓からのブドウ糖の産生調節に中心的な役割を果たすことを解明。空腹時のグルカゴンによってCITED2が増加すると、肝臓からのブドウ糖の産生が増強し血糖値が高くなり、この作用は肝糖産生を増強する糖新生系酵素の遺伝子発現誘導に重要な分子PGC-1αの活性化を介していることを見出した。 PGC-1αはGCN5というアセチル化酵素によってアセチル化修飾を受けると、その活性が抑制される。グルカゴンにより調節を受けるCITED2の機能に関する研究から、CITED2とGCN5の複合体形成が肝における糖新生誘導に中心的な役割を果たす可能性があるという。 第56回日本糖尿病学会年次学術集会
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]