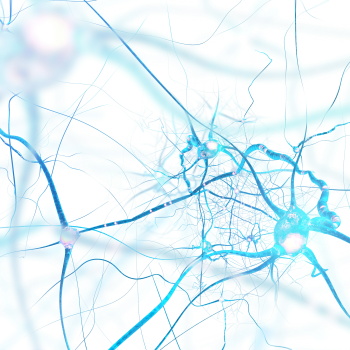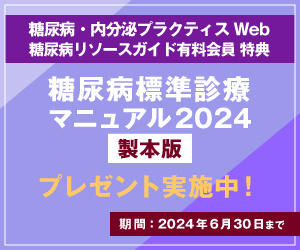抗肥満作用のあるベージュ脂肪細胞を増やす新たな治療法 基礎代謝を高め血糖値が改善 富山大学
2018.10.11
富山大学の研究グループは、抗肥満作用を有するベージュ脂肪細胞の調節メカニズムを解明したと発表した。脂肪組織中の特定のマクロファージを除去することで、褐色化が促され、血糖値が改善するという。2型糖尿病や肥満の新しい治療方法の開発につながる成果だ。

抗肥満作用を有するベージュ脂肪細胞の調節メカニズムを解明
富山大学の研究グループは、脂肪組織中の特定のマクロファージ(M2マクロファージ)を除去することで、寒冷時の適応として基礎代謝を高めるために起こる脂肪組織の「褐色化(ベージュ化)」が促され、基礎代謝が高まって血糖値が改善することを見出した。 脂肪組織には、エネルギーを貯蔵する白色脂肪細胞と、熱産生により体温を保つベージュ脂肪細胞がある。ベージュ脂肪細胞は、常温では白色脂肪細胞であるが、寒冷暴露により褐色化し熱産生を行う機能を持つようになる細胞であり、その活性化は抗肥満かつ抗糖尿病作用があることから注目されている。 M2マクロファージは脂肪組織に常在しており、肥満で増加し2型糖尿病などの代謝疾患の誘因となるM1マクロファージと区別されている。 M2マクロファージが脂肪組織のベージュ化を調節する役割を明らかにすることで、内臓脂肪や皮下脂肪と異なる、基礎代謝を高めるため肥満予防作用があるベージュ脂肪細胞を増やす新規の治療法につながることが期待される開発できる可能性がある。 研究は、富山大学大学院医学薬学研究部(医学)内科学講座1の戸邉一之教授、藤坂志帆助教、五十嵐喜子研究員、アラーナワズ研究員らの研究グループによるもので、英科学誌「Scientific Reports」オンライン版で公開された。
前駆ベージュ脂肪細胞の数の調節にM2マクロファージが関与
一般に肥満の予防に有効な手段として、過食を避ける、運動でエネルギーを消費する方法があるが、個人の生活習慣改善によるもので、実践が困難であることが少なくない。 そこで研究グループは、基礎代謝を高めてエネルギーを燃やす方法に着目。基礎代謝を高める作用のある脂肪組織の「ベージュ化」を促進するベージュ細胞機能の新たな調節の機序の解明に取り組んでいる。 寒冷な状態ではエネルギーを燃やして体温を維持するため、皮下の白色脂肪の性質が変化したベージュ細胞が出現する。ベージュ化が促進されると基礎代謝が高まり、抗肥満作用、2型糖尿病予防効果が期待できる。 一方で、脂肪組織にはさまざまな免疫細胞が存在し、肥満の病態ではこの免疫細胞のバランスが破綻する。研究グループは、免疫細胞の中でとくにM2マクロファージの役割に着目。 生体内のM2マクロファージだけを任意のタイミングで除去することができる遺伝子改変マウスを作成し解析したところ、寒冷時には正常のマウスで皮下脂肪のベージュ化が起こるが、M2マクロファージを除去しておくと、このベージュ化がより強くみられ、基礎代謝が高まって血糖値が低下し、インスリンの効きも良好な体質になることを突き止めた。 さらにこのベージュ化は、皮下脂肪にある前駆ベージュ脂肪細胞の数が増えることにより起こることも判明。前駆ベージュ脂肪細胞の数の調節にM2マクロファージが関与しており、M2マクロファージを除去することでベージュ化を高め、より基礎代謝の高い肥満しにくい体質に改善できる可能性があるという。M2マクロファージは肝臓や骨格筋などにもある
M2マクロファージを除去あるいは減少させることにより、エネルギー貯蔵型の白色脂肪組織から、エネルギー燃焼型のベージュ脂肪組織へ脂肪組織の性質を転換させ、より基礎代謝が高く、肥満しにくい体質に改善できる。2型糖尿病や肥満などの新たな予防法の開発につながる可能性がある。 M2マクロファージは肝臓や骨格筋など体内のほかの臓器にも存在している。研究グループは今後の研究で、脂肪組織以外の臓器のM2マクロファージの役割も明らかにしていくという。 富山大学附属病院第一内科Partial depletion of CD206-positive M2-like macrophages induces proliferation of beige progenitors and enhances browning after cold stimulationt(Scientific Reports 2018年10月1日)
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]