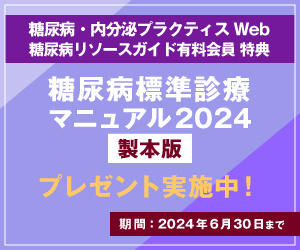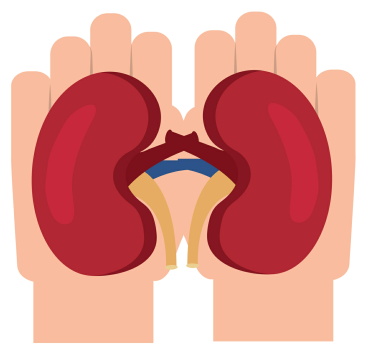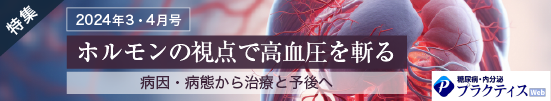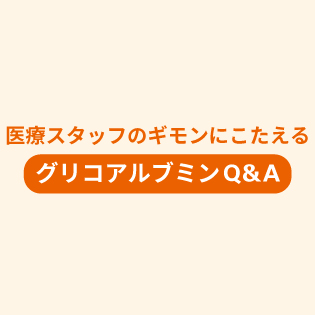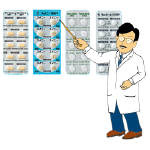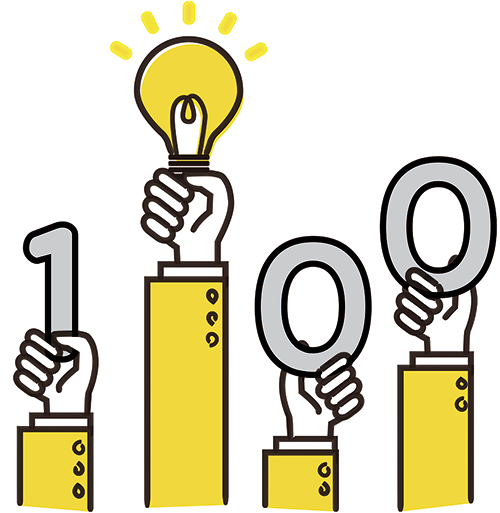ニュース/最近の関連情報
医薬品・医療機器・検査機器
-
経口薬
-
注射薬
-
医療機器・検査機器
学会・イベント
特集・連載
関連情報・資料
-
肥満症認知向上プログラム【セミナーレポート】
肥満症の基本から患者さんへのアプローチ、新ガイドラインを踏まえた診療、減量・代謝改善手術などの新たな治療選択肢など -
医療スタッフのギモンにこたえる グリコアルブミンQ&A
血糖コントロール指標である”グリコアルブミン”の基本から使い方まで、医療スタッフの皆さんの疑問にこたえるQ&Aコーナー。 -
新・糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント
加藤内科クリニック院長の加藤光敏先生が、ご自身の知識と経験を踏まえた服薬指導のポイントをわかりやすく解説。 -
関連資料・研究・調査・組織
調査や統計、学会・研究会・医界などの組織、財団・協会・支援基金、大規模研究や他のメディアなど、糖尿病や生活習慣病に関するリンク集。 -
糖尿病ネットワーク
糖尿病患者さんとそのご家族をはじめ、糖尿病医療に携わる医師、医療スタッフ、関連企業の方々などに向け、糖尿病に関する密度の濃い専門情報を発信。 -
国際糖尿病支援基金
国際糖尿病支援基金では、途上国の糖尿病患者さんがおかれた状況を紹介し、同じ糖尿病の仲間として何ができるかを考えます。豊富な海外の糖尿病事情をご覧ください。